離婚の際の財産分与とは?対象となる財産や流れをわかりやすく解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚する際、夫婦で貯めていた預貯金や夫婦で購入した家や自動車などは「財産分与」として夫婦で分け合います。
財産分与は、対象となる財産が多く存在したり、権利関係や価値の把握が複雑だったりして、離婚時に争いとなるケースが少なくありません。
本記事では、財産分与の種類、財産分与の割合、財産分与の方法など「財産分与」の基礎知識を身につけていただけるよう、様々な角度から詳しく解説していきます。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談するこの記事の目次
離婚時の財産分与とは
離婚時の財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築きあげた財産を、離婚時に夫婦それぞれの貢献度に応じて分けあうことをいいます。
民法768条第1項は、離婚時に相手に対して財産の分与を請求することができると定めています。
「財産分与」について、動画でわかりやすく解説していますので、ぜひご視聴ください。
財産分与の割合は「原則2分の1」
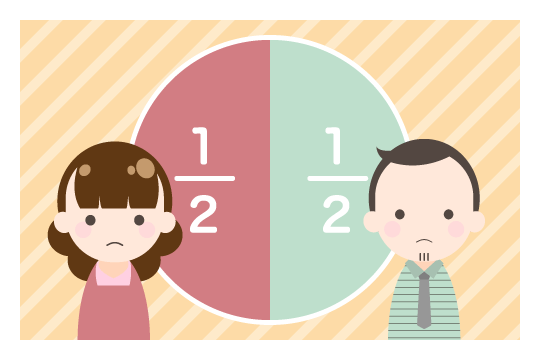
財産分与は夫婦の貢献度に応じて分け合います。
夫婦の婚姻期間中の貢献度は等しいと考えられていることから、財産分与の割合は、原則2分の1となります。
夫が会社員、妻が専業主婦の場合でも、夫が主に収入を得ていますが、妻が家事・育児をして家庭を支えているからこそ、夫婦が協力して財産形成・維持ができたと考えられるため2分の1の割合となります。
共働きの夫婦も、収入額に差があったとしても、夫婦が協力して財産形成・維持ができたと考えられるため、基本的に財産分与の割合は2分の1となります。
なお、離婚する原因が相手の浮気やDV・モラハラなど責任のある行為であっても、財産分与は原則2分の1の割合で分け合います。
「専業主婦の方の財産分与」について、「共働きの方の財産分与」について、それぞれ下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
財産分与の3つの種類
財産分与には、次表のとおり「清算的財産分与」、「慰謝料的財産分与」、「扶養的財産分与」の3つの種類があります。
| 清算的財産分与 | 夫婦が婚姻中に築きあげた財産の清算 |
|---|---|
| 慰謝料的財産分与 | 相手を傷つけたことに対する慰謝料の要素を含むもの |
| 扶養的財産分与 | 離婚により生活が困窮する相手の扶養 |
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
清算的財産分与
夫婦の共有財産を分け合って清算することを目的にしたもので、「夫婦で協力して築いた財産なのだから、2人で公平に分け合い清算しましょう。」という考え方のもと行う財産分与です。
あくまで目的は清算することですので、離婚原因には左右されません。一方の原因で離婚することになったとしても、2人で財産を分け合うことが可能です。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、配偶者の有責行為によって、夫婦のもう一方が被った精神的苦痛を加味して行われる財産分与をいいます。
本来は、財産分与は夫婦の共有財産を分配するものであり、慰謝料は離婚原因を作った配偶者が夫婦のもう一方の精神的苦痛の償いをするものであり、性質が異なります。
しかし、慰謝料と財産分与ともに離婚に伴う金銭の移動が問題になるため、慰謝料と財産分与を明確に区別せずに、離婚に際してまとめて「慰謝料的財産分与」として考慮することもできるとされています。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によって、清算的財産分与と慰謝料的財産分与をしたとしても、生活に困ってしまう夫婦のどちらか一方に対して、収入のある側から支払われるサポート目的の財産分与をいいます。
例えば、長年専業主婦(主夫)ですぐには経済的な自立ができない場合や、病気で療養が必要な場合などです。
扶養的財産分与の目的の性質上、物ではなく毎月一定の現金を受け渡すという方法で実現されるケースが多いです。金額やどのくらいの期間支払うかは当事者間で相談して決めますが、相場として、月に数万円程度の必要最低限の金額を半年から3年というのが目安になるでしょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0120-979-164
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する財産分与の対象(共有財産)
婚姻中に夫婦の協力により築きあげた財産を「共有財産」といいます。
共有財産の名義は夫婦どちらか問いません。
財産分与の対象となる共有財産は主に次のようなものです。
- 不動産(家、マンション、土地など)
- 自動車
- 退職金
- 年金
- 借金やローンなどの負債
- 生命保険や学資保険の解約返戻金
- 現金、預貯金
- 有価証券、投資信託
- 美術品、貴金属
特に財産分与する際に注意が必要なものは次項で詳しく説明しておきましょう。
現金、預貯金
基本的に、結婚したときから別居したときまでに蓄えた現金・預貯金については共有財産となりますので、財産分与の対象です。具体的に、共有財産かどうかについては以下のような基準で判断できます。
- 夫婦どちらの名義かは問わず、子供名義の預貯金であっても、夫婦の収入から蓄えたものであれば共有財産となる
- 相手に隠して蓄えたお金、つまり「へそくり」であっても、婚姻中の収入・資産で蓄えたものは共有財産となる
- 独身時代に蓄えた現金・預貯金や、親からもらった現金・預貯金は、個人が得た財産である「特有財産」であり、財産分与の対象とならない
不動産
婚姻してから夫婦が得た収入や資産などで購入した家、マンション、土地などの不動産は、財産分与の対象となります。
不動産を財産分与する方法は、主に①売却して代金を分ける方法、➁夫婦の片方が不動産に住み続けて、他方はその不動産の評価額の半額相当を現金で受け取る方法があります。
なお、独身時代に保有していた財産や遺産相続によって取得した財産で不動産を購入した場合や、遺産相続や生前贈与によって得た不動産は、特有財産となりますので財産分与の対象とはなりません。
また、住宅ローンの残額が評価額を上回る場合も、不動産の価値はないとみなされて財産分与の対象となりません。
「家を財産分与する方法」、「土地を財産分与する方法」は、それぞれ下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
自動車
婚姻中に夫婦で自動車を購入した場合は、財産分与の対象となります。
財産分与の方法としては、①自動車を売却して代金を分ける方法、➁自動車を売却せずに夫婦の片方が取得して、他方はその自動車の評価額の半額相当を現金で受け取る方法があります。
なお、夫婦のどちらかが独身時代から所有して自動車や、親族から遺産相続や生前贈与された自動車などは夫婦が協力して形成・維持した資産とはいえないので、財産分与することはできません。
また、自動車の残ローン額が評価額を上回る場合にも、自動車の価値はないとみなされるため財産分与の対象となりません。
自動車の財産分与について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
退職金
退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられるため、財産分与の対象となります。
ただし、退職予定日までに長く期間があるときは、会社の経営状況や退職理由などによっては退職金が支払われない可能性があるため、財産分与の対象となりません。
退職金の支給がほぼ確実である場合に財産分与の対象となります。
また、退職金の支給がほぼ確実であっても、退職金全額が財産分与の対象となるわけでなく、婚姻期間に応じた部分のみが対象となります。
なお、会社の経営状況等の将来の不確定要素は、その蓋然性がある場合を除いては考慮外とし、累積金額から同居期間に対応する部分について、財産分与の対象とするのが今日の実務の大勢です。
退職金の財産分与について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
年金
年金は、ほかの財産とは異なり、財産分与とは別の「年金分割」という制度で考えます。
年金分割とは、婚姻中に納めた年金保険料の実績を、離婚時に夫婦間で分割する制度です。分割する割合は、最大で2分の1とされています。
年金分割の対象となるのは、「厚生年金」と、現在は厚生年金に統一されている「共済年金」です。同じ公的年金でも、「国民年金」は対象になりませんので注意しましょう。
年金分割のしくみは、下記の記事でご確認ください。
合わせて読みたい関連記事
借金やローンなどの負債
夫婦が生活していくために負った借金やマイホーム、マイカーを手に入れるための住宅ローン、自動車ロ―ンなどは財産分与の対象となり得ます。
一方で、ギャンブルやブランド品の購入が目的での借金は、夫婦が生活していくために負った借金といえませんので、財産分与の対象となりません。
例えば、共有財産がマイホームとその住宅ローンしかない場合、ローン残高が不動産評価額を下回っているとき(アンダーローン)は、差し引いた金額が財産分与の対象となります。
一方で、ローン残高が不動産評価額を上回っているとき(オーバーローン)は、不動産に価値がないとみなされ、財産分与の対象となりません。
「離婚時に債務があった場合の財産分与」については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひ、ご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
生命保険や学資保険の解約返戻金
家族のことを考えて結婚後に加入した生命保険や学資保険のなかには、解約すると「解約返戻金」が支払われるものがあります。こうした保険は財産分与の対象となり、解約した場合は解約返戻金そのものを、解約しなかった場合は解約返戻金の見込み額を分け合います。
ただし、結婚する前に貯めていたお金で保険料を支払っていた期間があると、その期間に相当する解約返戻金は財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象外(特有財産)
夫婦の一方の力のみで得た以下のような財産を「特有財産」といい、財産分与の対象外となります。
- 独身時代から保有していた財産
- 婚姻中に親や親族から遺産相続や生前贈与した財産
- 別居後に夫婦それぞれが取得した財産
ただし、特有財産であっても、夫婦の協力によって財産の価値が維持されたり、価値が増加したりしたといえる場合は、財産分与の対象となる場合もあります。
財産分与の方法と流れ
財産分与の方法は、次のような様々な方法で行えます。
- 不動産や自動車などの対象財産を自分が取得する代わりに、相手にその対象財産の価値の半分相当額を金銭で支払いをする方法
- 対象財産を売却して、売却して得た金銭を分け合う方法
- 対象財産の現物を分け合う方法 など
次に財産分与は、主に次のような流れで行っていきます。
① 対象となる財産を把握する
② 夫婦間で話し合う
③ 調停や裁判に移行する
次項より、それぞれ詳しく解説していきます。
対象となる財産を把握する
まずは、財産分与の対象となる財産を洗い出し、それぞれ根拠となる資料を揃えます。
例えば、預貯金通帳のコピー、保険証券、不動産固定資産税評価証明書、車検証、退職金が分かる資料などが挙げられます。
不動産や自動車などは、基本的に現在の価値が財産分与の算定基準になりますので、専門業者に査定してもらう必要があります。
住宅や自動車のローン返済中の場合は、現在のローン残債をローン会社に確認してください。
また、自分の財産はきちんと把握していても、相手が保有・管理している財産についてはわからない場合があります。
相手の財産がわからない場合は、銀行や保険会社などから封書やハガキが届いていないか確認してください。届いていれば、その銀行や保険会社などに財産を保有している可能性があります。
郵便物を確認してもわからない場合は、相手に直接すべての財産を開示するように求めていきます。
任意の財産開示に応じてもらえない場合は、弁護士に依頼して弁護士会照会という方法や、裁判所の手続きに進んでいるときは裁判所を通して調査嘱託の申立てをして、相手の財産を明らかにしていきます。
財産分与での通帳開示については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
夫婦間で話し合う
夫婦間で財産分与について話し合います。
具体的に分割割合、分割方法、受け渡し方法などを決めます。
財産分与は、基本的に夫婦それぞれ2分の1ずつに分け合いますが、夫婦間で合意できれば自由に財産分与の割合を決めても問題ありません。
話し合いで財産分与について合意できたら、合意内容を書面に記載して残しておくようにしましょう。
できれば、書面は強制執行認諾文言付公正証書にしておくと、あとで相手が合意内容に反して、財産分与をしなかった場合に強制執行をして相手の財産を差し押さえられます。
なお、財産分与は請求期限が存在し、「離婚から2年以内」となっています。
期限を過ぎると、基本的に財産分与を請求できなくなりますので、できるだけ早く財産分与について話し合うことをお勧めします。
調停や裁判に移行する
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。
調停は、裁判官や調停委員を介して話し合いで解決を図る手続きです。
調停では、裁判官や調停委員から法的な説明や和解案が示されるため、合意できる可能性が高まります。
それでも合意できなかった場合は、最終手段として裁判を提起する方法があります。
裁判では、裁判官が一切の事情を考慮して、財産分与について判断を下します。
財産分与をしない方法はある?拒否できる?
財産分与は、相手から請求されたら基本的に拒否できません。
夫婦間の話し合いの段階でいくら拒んだとしても、訴訟等の法的手続に移行した場合には、法律にしたがって財産分与を行うことになります。
また、財産分与はどちらに離婚原因があるのかは関係ありませんので、相手の浮気・不倫やDV・モラハラなどが原因で離婚に至った場合でも、相手から財産分与について請求されたら拒めません。
ただし、財産分与をしなくて済むケースもあります。
具体的には、次のような状況です。
- 話し合いで財産分与はしないと合意した場合
- 配偶者が財産分与請求権を放棄した場合
- 離婚から2年以上経過している場合
- 婚前契約で財産分与はしないと定めていた場合
- プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)の方が多い
などです。
「財産分与したくないときにやっておいたほうがいいこと」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚の財産分与を弁護士に依頼するメリット
財産分与については、弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられます。
財産分与の対象となる財産を正確に把握できる
財産分与は、相手が正直に財産を開示するとは限らず、ほかの財産の存在が疑われる場合などがあります。
弁護士に依頼すれば、弁護士会照会や、裁判所を通した調査嘱託の申立てを行って、相手の財産をきちんと把握できます。
適切な財産分与ができる
財産分与のポイントがわからないまま自分で進めてしまうと、獲得できたかもしれない財産を相手に取られてしまったり、渡さなくていい財産を渡してしまうおそれがあります。
弁護士に依頼して進めれば、法的知識に基づいて適切な財産分与が可能となります。
時間の節約や、精神的負荷の軽減につながる
財産分与は、離婚条件のなかでも特に争いとなることが多く、当事者間の対立が激しくなる事項です。
弁護士に依頼すれば、交渉や、調停・裁判などの裁判所の手続きを一任できますので、時間や労力はかかりませんし、精神的な安定にも繋がります。
離婚の財産分与に関するQ&A
- Q:
-
財産分与で家を受け取る場合、名義変更はしたほうがいいですか?
- A:
-
財産分与で受け取ることになった家の名義が相手になっているのであれば、名義変更をしてご自身の名義にしておいたほうがいいです。
名義変更をしなかった場合、家の所有名義人は相手のままとなるので、勝手に売却されてしまうリスクがあり、もし売却されてしまったら取り戻すことは困難です。こういったトラブルに見舞われないよう、財産分与で家を受け取る場合には、きちんと名義変更をしておきましょう。
下記の記事では、財産分与時の家の名義変更について詳しく解説しています。名義変更の方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
-
婚姻期間中にそれぞれで貯めた貯金も財産分与の対象になりますか?
- A:
-
婚姻期間中に夫婦がそれぞれに貯めた貯金も、基本的には財産分与の対象になります。
結婚して共同生活を送っている以上、夫婦それぞれが自身の名義で貯金して財産を増やしても、お互いに支え合ってきたからこそ財産が増えたと考えられるためです。ただし、婚姻期間中とはいえ、別居後に得た財産は夫婦の協力によって築かれたとはいえないため、財産分与の対象には含まれないのが通常です。
財産分与と婚姻期間の関係について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
-
財産分与をした場合、税金はかかりますか?
- A:
-
財産分与は、基本的に税金(贈与税)はかかりませんし、確定申告も不要です。
離婚時の財産分与は、贈与ではなく、夫婦の共有財産の清算や離婚後の生活保障のために財産分与請求権を行使して給付を受けたものだと考えられるためです。ただし、例外的に税金がかかる場合があります。
具体的には、財産分与の原則ルールにしたがった場合に比して、分与額が著しく高額である場合や、贈与税や相続税を免がれるために故意に離婚したとみなされる場合などです。税金がかかる可能性がある場合の税金の種類は、受け取る側、渡す側それぞれ次表のとおりです。
受け取る側 渡す側 現金・預貯金 贈与税 - 不動産 贈与税、不動産取得税 譲渡所得税 株式など 贈与税 譲渡所得税 財産分与にかかる税金について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
- Q:
-
離婚時の財産分与で、貯金を隠すとどうなりますか?
- A:
-
離婚時に貯金を隠しても刑事罰はありません。
しかし、民事上の不法行為または不当利得とされる可能性があり、相手が損害を受けたという事実があるならば、損害賠償請求される可能性もあります。
民事上の請求のほかに、離婚から2年以内であれば、財産分与のやり直しが可能な場合もあります。貯金を隠していることが相手に知られれば、新たな紛争が起こる可能性が高いため、嘘をついたり隠したりせずに、公平に財産分与することをお勧めします。
離婚での財産分与の話し合いが進まない場合は、弁護士にご相談ください
離婚後に安定した生活を送るためにも、財産分与は公平かつ正確に行うべきです。
しかし、自分では、財産分与の対象となる財産について、判断しにくい場合もあります。
離婚する際に財産分与で損をしないためにも、ぜひ、弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGでは、離婚問題をたくさん取り扱っており、経験豊富な弁護士が多数在籍しています。できる限りご自身の希望に叶い、有利な条件や内容で離婚できるように、全力でサポートさせていただきます。まずは、お気軽にお問合せください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
弁護士法人ALG&Associates 事務所情報
お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
- 関連記事
- 離婚したらペットはどちらが引き取る?養育費や面会はどうなる?財産分与で家はどう分ける?離婚時の分与方法や注意点などを解説離婚に伴う財産分与、確定拠出年金はどうなる?子供名義の預貯金は財産分与の対象?学資保険についても解説財産分与にかかる税金とは?節税方法も含めた基礎知識専業主婦でも財産分与は受けられる?対象となる財産や割合など共働き夫婦の離婚に伴う財産分与はどうする?離婚時の財産分与 ローンが残っている財産はどうなる?離婚の財産分与による不動産の名義変更|ローンがある場合の注意点や手続きの流れポイントカードを財産分与する方法車は財産分与の対象になるのか。分ける方法と割合について離婚時に財産分与をしたくないときにしておいたほうがいいこと離婚時に退職金は財産分与の対象になる?もらえる金額の計算方法土地を財産分与する方法財産分与での通帳開示 | 通帳の預貯金はどこまで分与対象か離婚の際に借金がある場合は財産分与の対象になる?へそくりは財産分与の対象になるのか離婚時の財産分与で子供のために考えること離婚の財産分与と婚姻期間の関係株は財産分与の対象か












